経営の進化
人事のプロ、そして事業成長の請負人。CARTAで活躍する「HRBP(HRビジネスパートナー)」のリアルとは?
「守り」を超え事業を「創る」人事へ
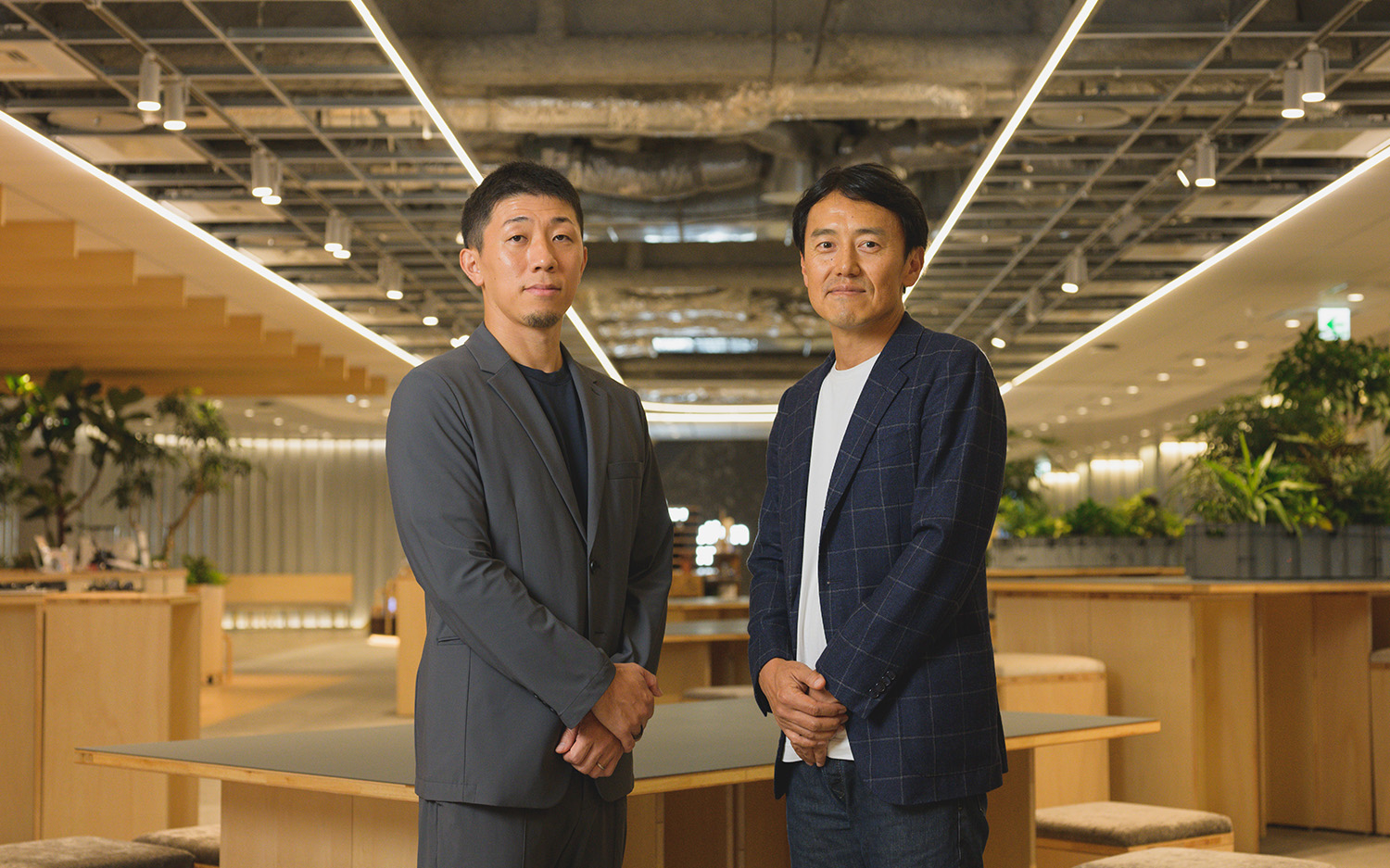
本記事では、HR本部 本部長の小椋 祐二とCARTA ZEROで取締役COOを務める西園 正志が、CARTAにおけるHRBPのあり方や取り組みの現在地を、HR部門と事業部門、それぞれの視点から明かします。

小椋 祐二
Yuji Ogura
株式会社CARTA HOLDINGS
執行役員HR本部長

西園 正志
Masashi Nishizono
CARTA HOLDINGS 上級執行役員
株式会社CARTA ZERO 取締役COO
CARTAのHRBPは、“組織”と“人”の側面から事業を伸ばすパートナー
―はじめに、HRBP(※)という役割を設置した背景を教えてください。
小椋 祐二(以下、小椋): CARTAでHRBP機能を置いているのは、我々HR部門が事業成長にコミットする姿勢を明確にするためです。
従来、多くの企業の管理部門は「法的リスクを回避し、経営が安心して回るよう管理・運用する部門」と考えられていて、HR部門も同様でした。この役割は今も変わらず重要ですが、「事業を成長させるのは事業部門の仕事」という、どこか他人事のような捉え方につながりやすい側面もあったと思います。
CARTAのHR部門は管理や後方支援に閉じてしまうのではなく、事業成長というミッションを一緒に作り上げる部門でありたい。そのためにHR部門内の職種の一つとして、HRBPを設置しています。
私自身は、2000年にCARTAの前身企業に入社し、約20年間、事業部側で営業などを担当してきました。2022年にHR部門に異動したのですが、この経験から、人事が事業部に対して営業マインドを持ち事業成長へ貢献するという視座で活動する重要性を認識しています。
実際に、HRBPの機能が拡大するにつれ、事業部門のニーズを迅速にキャッチできるようになってきました。同時にHR側から見た課題も、事業部門にしっかりフィードバックできるようになりました。

※HRBP(HRビジネスパートナー:Human Resource Business Partner)=ミシガンビジネススクールの教授 デイブ・ウルリッチ氏が提唱した概念。人事機能のなかでも事業部門の経営者や責任者のパートナーとして、事業成長を人と組織の面からサポートする役割を担う。CARTAではHRBPに4つの役割(戦略パートナー、変革のエージェント、従業員チャンピオン、管理のエキスパート)を求めている。
―日本ではHRBPを設置している企業はまだ多くなく、HRBPが担う役割も、企業によってやや異なるようです。CARTAのHRBPは、どのような考え方やスタンスで事業に携わっているのでしょうか。
小椋: CARTAにおけるHRBPに求める仕事のスタンスは、クライアント営業に近いと思います。
営業がクライアントのビジネスを深く理解した上で、クライアントのビジネス拡大のためにソリューション提案をして実行支援をするように、HRBPも事業部をクライアントと捉え、どうサポートすれば組織や人を成長させられるか、自分がどこで価値を発揮できるかを考えます。
営業が競争環境の中で能動的に動くことで信頼と成果を上げるように、HRBPも自ら働きかけることで信頼を積み、活動と成果で価値を生み出していきます。
―西園さんは事業部側のトップとして、HRBPにどのような期待をしていますか。
西園 正志(以下、西園): 「人事も事業成長のためにいる」「人事も事業の一機能である」と捉えて、事業成長にコミットしてくれる存在であってほしいと思います。
事業部門や経営のトップにとって理想的なのは、組織のメンバーが経営や事業の方針を理解し、長くコミットして力を発揮してくれる状況です。そのためには、メンバー一人ひとりのコンディションを把握し、適切な働きかけをする必要があります。
ですが、縦のラインだけでは状況を把握しきれなかったり、メンバー側も直接相談しにくかったりすることがありますよね。ここにHRBPの価値があると思います。HRBPが第三者的に存在することで、客観的に状況を把握し、適切な対応ができるようになります。
また、HRBPには「御用聞き」にとどまらないでほしいとも思っています。「誰々がこういう状態です」という報告だけでなく、「だからこうしませんか?」という解決策の提案まで、セットで持ってきてくれると心強いです。

「一緒に事業を作る仲間」と捉え、情報を開示し権限も移譲
―CARTAでは既に数名のHRBPが活動していますが、日々どのように業務を進めているのでしょうか。
小椋: 現在、約1,500人のホールディングス社員に対して8名のHRBPで対応しています。基本的には個人が担当の会社や事業部門を持って対応していますが、西園さんがCOOを務めるCARTA ZEROのように規模が大きい組織には、4〜5名の担当者を配置しています。
HRBPはそれぞれの事業会社の経営会議などに参加させてもらい、経営課題や情報に触れながら、そこから見えてくる組織や人の課題に対応していきます。顕在化した問題や課題に対して、事業責任者から相談をもらうケースもありますし、HRBPが潜在的な課題を発見するところから始めるケースもあります。
事業部門の状況は日々変化しますし、組織や人の課題も多岐にわたります。すべてに対応するのは現実的ではないので、優先順位をつけながら、限られた時間の中で最大の効果を生み出していく判断力も必要になります。
また、事業部門の経営陣や現場のメンバーと信頼関係を築くコミュニケーション力も欠かせません。
西園: HRBPに対しては、事業状況などの情報を開示できるものはすべて開示していますし、権限も移譲しています。
経営陣や事業部長を後方からサポートするのではなく、日々苦楽をともにし、一緒に事業成長を作っていく。この働き方が、CARTAのHRBPの大きな特徴だと思います。
経営の意思決定に近い場所で動くからこそ、HRBPは事業の方向性を深く理解でき、タイムリーで実効性の高い施策を打つことができます。また、事業部側のメンバーも「人事は別の部署」ではなく「一緒に事業を作る仲間」と認識するようになります。
―やりがいが大きい一方で、難易度が高い仕事でもあると思います。HRBPがうまく成果を出せるよう、HR部門として何かサポートをしていることはありますか。
小椋: サポート体制はしっかり整えています。労働法や就業規則といった法律・規則、採用や育成、パフォーマンス管理などの人事業務の基礎知識については、HRBP内で読書会を開催したり、書籍購入補助などを通して自己学習をサポートしたりしています。また、HRBP特有のスキルについては、外部の講座受講の機会を提供しています。
各事業部を個人が担当する働き方をしていますが、HRBP同士のつながりも強いです。Slackや日常的なチームミーティング、人事全体の定例などで、それぞれの案件や対応例をシェアし、複眼的にレビューしています。
こうした横のつながりは、心理的な支えとしても、また人事としての専門性を高めるチャンスとしても、価値があると思います。さまざまな事業部の事例に触れることで、自分の担当領域だけでは得られない引き出しを増やすことができます。

事業貢献を成果指標に、広範囲の改善活動をリード
―西園さんからHRBPへの情報共有のお話がありましたが、ほかにも事業部としてHRBPが成果を発揮できるように気をつけていることがあれば教えてください。
西園: 中長期的な視点で、組織の課題やHRBPの働きをトラッキングする仕組みを作りました。
人事の仕事は、営業のように結果が数字でわかりやすく可視化されるものではありません。また、日々さまざまな課題が生まれていく領域なので、狙いを定めなければ場当たり的な対応になりやすい側面があります。だからこそ、まずは、戦略人事として機能するための土壌を整えようという話になりました。
具体的には、「サービスを受けている事業部側からの評価をきちんと取ろう」と決めました。元々全社で実施していた半年に1回の満足度調査に加えて、「この期間のHRBPの働きは、事業成長に貢献できていますか」といった、事業貢献度を問うアンケートも取るようにしました。
そうすると基準ができるので、「次の半年間では、この数値を上げていこう」と狙いを定められます。HRBPチームとも「どういう施策を打ったらいいか考えてきて」「こういうことをやっていきます」といったコミュニケーションが生まれ、実際にいくつかの施策が走り始めました。数値で追えるようになったことで、HRBPも自分たちの働きの成果を実感しやすくなったと思います。
―事業成長に向けて目線を合わせながら動ける環境が整ったのですね。別の観点として、CARTAでは日々新しく事業が生まれており、それに伴う組織改編も行われると思います。このような場面でも、HRBPは活躍しているのでしょうか。
小椋: はい、組織改編はまさにHRBPが活躍する場面です。事業側は必要性を感じて組織改編を行っているので、なるべくスピーディに対応していく必要があります。
一方で、そういった変化の時には現場でさまざまな課題や混乱が生じます。たとえば、ワークフローはどうなるのか、働いている人のモチベーションコントロール、組織をどう作るかといった課題です。
2023年10月にグループ内のデジタルマーケティング系4社が統合して株式会社CARTA MARKETING FIRM(以下、CMF。現CARTA ZERO)という新会社が発足したのですが、そこを担当したHRBPは素晴らしい働きをしています。CMFは統合直後から組織拡大を急ぐ必要があり、毎月中途で数名が入社していました。社内の統合と並行して、オンボーディングも整備すべき状況だったのです。
そこでHRBPは、まずCMF全員に知ってほしい情報と部門固有の情報を切り分け、統合前4社のオンボーディング内容を吸い上げて、CMFとして最適なフローを構築しました。結果として、統合前は60%の新入社員が何かしらの困りごとを抱えていたのが、フロー整備後には16.7%まで改善しました。
さらに事業部のDX推進局とも連携して、「CMFポータル」という情報のストック場所も作り、新入社員だけでなく、すべての社員が業務で困ったときに見返せる場所として機能させたり、その後も業務フローの改善など、従来の人事の概念に囚われない活動をしています。これは、事業成長を支える基盤づくりそのものです。

深い事業理解とプロアクティブな姿勢が活きるポジション
―HRBPをCARTAでやることの魅力について教えてください。
小椋: 何と言っても事業部門側との距離の近さですね。CARTAはホールディングス一体経営の形態をとっており、原則社員全員がCARTAに所属し、事業会社に出向して働いています。
皆がCARTAにオーナーシップと高いエンゲージメントを持って働いているので、事業部門と管理部門が、お互いに向き合いながら協力して進められます。
特に採用活動でそれを感じます。経営から現場層まで、両部門が「自分たちの最重要ミッションだ」と捉え、協力して主体的に取り組むべきだという認識を持っています。
事業部門からHR部門に対し「全然採用できないじゃないか」といった声が上がる、採用活動はほとんど人事がお膳立てして事業側は面接だけ参加する、といった話を他社でたまに聞くことがありますが、CARTAではそのようなことは全くありません。
西園: 今の話はとても重要だと思っています。採用市場のなかで、我々はチャレンジャーであり、求人に応募してもらう、働き続けてもらう、という選択をしてもらう必要があります。ですから事業部サイドには、「我々は選んでもらう側。選ばれるためにどうするか考えていこう」と繰り返し伝えています。
だから採用にもコミットしますし、入社してくれたメンバーの動機付けも重要視しています。
このような姿勢で皆が取り組んでいるので、HRBPには「とりあえず今回のヘッドカウントは埋まりました」という考え方ではなく、もっと根源的に問題と向き合うことが求められます。
逆に言うと、そういうことに関心がある人にとっては、「こんなに深く入らせてもらえて楽しい」と感じていただけるのではないでしょうか。
―最後に、CARTAのHRBPとして働く上で活かせるスキルや経験、マインドとは何か、考えをお聞かせください。
小椋: 前提として、現時点で広い人事の知見と十分な実績を備えている人だけを採用するとは考えていません。私たちも理想的なHRBPの在り方を探っているところですので、一緒に試行錯誤し、成長してくれると嬉しいです。
その上で申し上げると、CARTAのHRBPには事業成長に対するオーナーシップとプロアクティブな姿勢が求められます。担当する事業がどんな市場で戦い、どんな収益構造で、何が成長ドライバーなのか。事業責任者がどんな人で何を考えているのか。こういったことを本気でキャッチアップし、学ぶ意欲がある人は、フィットすると思います。
スキル面では、課題を見出す力やプロジェクトマネジメント能力も重要です。事業責任者と一緒に成長を作っていくには、高い視座で本質的な課題を特定し、その重要度や緊急度を判断し、解決計画を立て、関係者を巻き込みながら実行していく力が必要です。
人事関連の経験はベースとして必要ですが、企業の人事部門出身でなくても構いません。採用やマネージャー育成など、組織や人に関わるミッションを自らリードして実績と成果を出した経験があると良いですね。
西園: 「事業成長のためにメンバーの可能性をどう引き出すか」が重要なので、事業側の事情も分かる方だと一緒に取り組みやすいです。「事業部門を対象に人材育成をやってきた」「人と話すのが好き」といったタイプの方は、ご活躍いただけると思います。



