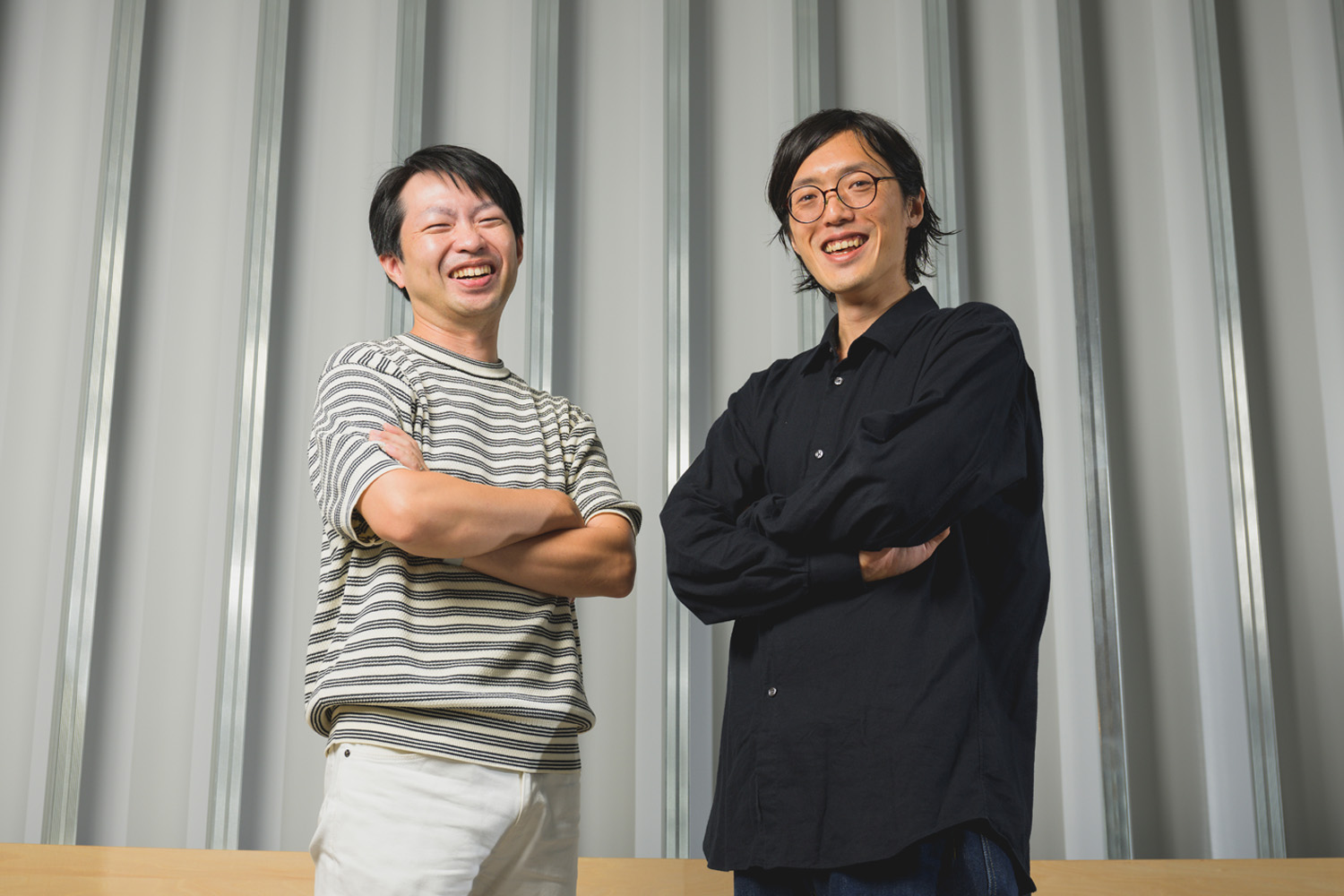事業の進化
多様な事業のド真ん中。AI変革をリードする「AI推進室」とは
「個人レベルのAI活用」に危機感、全社で「AIネイティブ」へ

※本記事内で「AI」はいわゆる「生成AIおよび関連技術」を指します。

加藤 友幸
Tomoyuki Kato
株式会社CARTA HOLDINGS
AI推進室 室長

鈴木 健太
Kenta Suzuki
株式会社CARTA HOLDINGS
執行役員CTO
共著『みんなのGo言語』(2016年 技術評論社)、『データ分析基盤構築入門』(2017年 技術評論社)。
目指すは“AIネイティブ”への転生。経営直下「AI推進室」誕生の裏側
―まずは、AI推進室が設立される以前の状況をお聞きします。生成AIの登場以降、CARTAではどんな取り組みが展開されてきたのでしょうか。
鈴木 健太(以下、鈴木): 2023年4月に「 CARTA Generative AI Lab 」(以下、AI Lab。社内向けにAI実装の技術的支援などを実施。)を立ち上げ、エンジニアを中心に開発業務へのAI活用が先行している状態が続きました。エンジニアに限らず活用してもらうために、汎用的な業務環境として、GoogleのAIアシスタント「Gemini」を全従業員向けに提供しています。
また、グループの e ラーニングサービス D-Marketing Academy ではAI特化の講座を立ち上げました。これをCARTAの従業員は無料で受講できます。

加藤 友幸(以下、加藤): AI Labが主体となり、各事業会社のニーズに基づいてこれまでに20程度の取り組みを進めてきました。鈴木が旗を振って生成AI利用ガイドラインを作成し、安心して利用できるように線引きもしました。
今では大半のエンジニアが日常的にAIを利用してコーディングを行っています。私個人としては、メディアの運用を半自動化する際にAIを多用し、コンテンツ制作工程の約90%を自動化することに成功しました。こうした事例はグループ各社にあります。
―AI Labがあり、また成果が上がっている中でなぜ「AI推進室」を立ち上げたのでしょうか。
鈴木: 成果が上がっていると言っても、AIを使えている人とそうではない人で差があり、「詳しい個人だけが積極的に使っている状態」でした。
AIの利活用につながる「業務課題とAI活用方法」の学びが組織全体に伝播しにくい状態だったのです。全社に広める取り組みも単発にとどまり、成果になるまで見届けられていませんでした。
AI Labは研究開発とその応用がメインのミッションですが、AI推進室は個人レベルと組織レベルのAIによる成功を隅々まで行き渡らせる役割を担います。
加藤: 2024年頃からAIエージェントが急激に普及しはじめ、2025年以降にあらゆる業務がエージェント化する未来が確定したと見ています。この猛烈な変化を全社でドライブさせる必要があり、そのためには部署も職種も関係なく全社を巻き込んだ推進が不可欠だと経営判断がなされました。
個人の意欲への依存、同じものの重複開発、評価基準のばらつき、学びが循環しないといった課題を是正し、人材を育てていく必要性を感じたのです。

―AI推進室として、AI活用に関して掲げているスタンスや、目指している具体的な目標があれば教えてください。
加藤: スタンスは「ミッション達成のために何でもやる」です。
私たちは、CARTAを単なるデジタルネイティブから、思考も、事業も、文化も、全てがAIを前提とする“AIネイティブ”な会社へ、本気で転生させようとしています。
CARTAには各事業会社が自律的に事業を運営する文化があります。私たちはその裁量を尊重しながらも、経営陣と一体となってAIの取り組みを加速させます。
全社で画一的で具体的な定量目標は持ちません。各事業会社によって向き合う産業だけでなく、事業ステージも異なります。画一的な全社目標は強力であるがゆえに、事業会社の運営上ノイズになると考えました。AI推進室は各事業会社が掲げた戦略目標を達成できるよう、横断的にリソースを提供し、全力で支援していく構想です。
社長が“即レス”で助け舟を出すことも。異常に速い意思決定の秘密
―AI推進室での二人の役割と、チームの雰囲気を教えてください。
加藤: 私はAI推進室全体のリードを担当し、パートナーシップなども含めてCARTA内部を巻き込んでいます。CTOの鈴木健太は技術的に最も良い方法をアドバイスしてくれます。社内チャットで即座に対話ができ、やりとりが非常に速いです。
速さの理由は経営直下のコミュニケーションの設計にあります。
CARTAの役員も参加するAI推進室の社内チャットがあり、経営会議を待たずとも迅速な意思決定が可能です。
例えば、外部の先進企業との連携を検討していた際、議論を見ていた社長の宇佐美から「この会社のキーマン知ってるから、すぐ繋ぐよ」とメンションが飛んできて、数時間後にはアポイントが確定していた、ということが日常的に起こります。
各事業会社の経営陣とも直接やりとりできる関係性ができているので、現場レベルでもスピードを落とさない体制ができています。
鈴木: また、AI Labと密に連携しています。AI推進室は自分たちで簡単なソリューションを作りますが、技術的な壁があればAI Labに相談します。Difyやn8nといった、オーダーメイドでAIツールを構築するためのソリューションとの連携が増えており、外部APIやナレッジの拡張ではエンジニアが個別に対応することもあります。データ連携や自動化で何かあればAI Labに相談するという流れです。
加藤: 隔週のAI推進室の定例ミーティングにはCTOの鈴木も参加するので、技術的な課題はその場で解消できます。また、AI推進室の社内チャットにはAI Labのメンバーも参加しており、事業部のニーズがリアルタイムで技術組織に伝わりやすい構造になっています。

求められるのは「AIに賭ける覚悟」。メンバーが明かす仕事のリアル
―AI推進室の主な仕事は、各事業会社の課題やニーズを理解しながら、AI活用を支援することです。具体的にどのようなプロセスで課題を発見し、解決策を設計していくのでしょうか?
加藤: AI推進室のプロジェクトマネージャーが各事業会社に入り込み、ヒアリングを通じて課題を整理し、業務フローを再構築することから始めます。
時間的コストが重いものを選定し、AIでどこまで実現可能かを見極めながらプロトタイプを構想・実装します。
実証実験が軌道に乗れば、社内サービス化を目指します。重要なのは、既存業務をAIに向く粒度まで細かく分解することです。
―AI推進を担う組織・役職を設置する企業は、徐々に増えています。CARTAグループでその役割を担う醍醐味は、どんな点にありますか?
鈴木: 今の仕事をもっとよくするにはどうしたらよいかを皆が考えているので、AIの登場はポジティブに受け入れられています。CARTAにはもともとデジタルやテクノロジーに関心が高い人が多いので、AI技術そのものを楽しんで使ってくれる人が多いですね。
加藤: デジタル親和性の高い人材が多く、「試す→計測する→直す」というサイクルへの抵抗が低いのも、特色ではないでしょうか。また、広告・マーケティング領域は、入稿・最適化・レポート・請求などエージェント化の余地が大きく、事業サイズも大きいためインパクトを作りやすいと感じています。
また、AI推進室に求められているのは、グループ内への働きかけに留まりません。CARTAのアセットとAIを組み合わせた新規事業開発をリードできる可能性もあります。事業開発においては、CARTAが多種多様な事業を展開していること自体が最大の強みになります。広告業界から人材業界まで幅広い産業で展開する、グループ内の事業会社の課題を直接吸い上げて事業化のシーズを探索できるため、新規事業のプロセスを大幅に短縮できると考えています。また、社内の複数の事業で共通して使えるエージェントを開発・検証することで、世の中に提供する前に磨き上げて、ソリューションを汎化しやすいと考えています。

AIによる変革を“当事者”として楽しみ、価値を作る
―AI推進室では現在、新しいメンバーを募集しているそうですが、共に働く方に期待するマインドセットや求める人物像について教えてください。
加藤: とにかくAIとその未来に興味があり、自分の人的資源をAIに賭ける覚悟を持つ人ですね。
各事業会社の役員と同じ視点で事業や組織を捉えて、事業課題を深く理解することが必要です。スタンスとしては、「経営マインド」「答えを出し続ける姿勢」「課題を第一とする主義」「データへの謙虚さ」、そして「AIをマネジメントする視点」です。
―最後に、この挑戦にかける、お二人の個人的な想いや情熱をお聞かせください。
加藤: AIは、インターネットの誕生に匹敵する、社会構造を変えるほどの革命的な技術だと確信しています。この変化を傍観者ではなく当事者として、誰よりも高いレベルで楽しみたいと思っています。AIの力で既存の顧客との関係をより深化させ、まだ見ぬ顧客に全く新しい価値を創造していく。CARTAはこれまでもテクノロジーの変化の波に乗って事業を拡大してきましたが、これからもその先頭を走り続けます。
鈴木: AIの進化はあらゆる事業を変える広大な可能性を秘めていると感じています。今来ているこの波もまだ序章であり、いずれ多くの「仕事」の前提が覆される時代が来ると予想しています。
技術的観点から俯瞰すると、現在世の中にリリースされている基盤技術を仮に5年後に振り返ったとしたら、「まだ発展過程だった」と言われることでしょう。2025年10月時点において、AIを応用した体験の創出、アプリケーションレイヤーの工夫、業務プロセスの磨き込みには非常に多くの余白が残されています。
あらゆる産業が変化するこの稀有なタイミングを全身全霊で楽しみ、自らの取り組みによって変化を生み出したいと考えています。