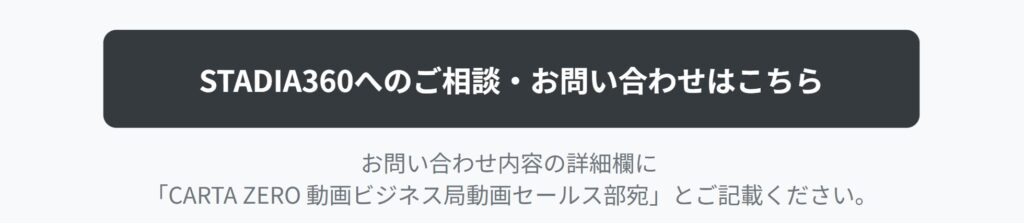事業の進化
テレビ視聴データで広告効果を最大化!「STADIA360」で実現する次世代デジタルマーケティング

著しい成長を見せる動画広告、そして最先端のデータマネジメントがタッグを組むと、どのような世界が見えるのでしょうか?それぞれの領域の最先端を走るプレイヤー達の会話から、そのポイントを探ります。
*1:2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」(CCI/電通/電通デジタル/セプテーニ)

原 玄 氏
Gen Hara
株式会社電通
データ・テクノロジーセンター
メディアコンテンツデータ部
シニア・プランナー

齋藤 麻衣
Mai Saito
株式会社CARTA ZERO
ブロードキャスティング管轄
動画ビジネス局 動画セールス1部
部長
高まる動画広告の存在感とデータ活用の重要性
―デジタルマーケティングの中で動画広告は高い成長を続けており、広告主にとっても活用の主軸になりつつあるものと思います。その背景は何だと思いますか?
齋藤:動画サービスが増加し、それにともなってマーケティングの需要が増えていることが一番の要因だと考えています。ユーザーに対してよりリッチなコミュニケーション表現が可能になったことで、広告会社および広告主側も動画広告の特性への理解が日々深まってきていることを実感しています。
原氏:電通グループ全体で見ても、動画関連の広告出稿が増えています。ユーザー目線では、地上波テレビに加えてVOD(Video On Demand:インターネットを通じて好きな時に好きな動画コンテンツを視聴できるサービス)も多様化しており、デジタル広告においてもリッチなコンテンツへのニーズが高まっているのではと感じています。

―動画配信サービスも様々なものがありますね。各メディアやプラットフォームでの広告活用において、特徴や違いはありますか?
齋藤:メディアやプラットフォームによってコミュニケーションの取り方に特徴があります。例えば、PremiumViewのメインの配信面であるTVerは、テレビでCMを放映していたものの、テレビを見られなかった層にも届けたいというニーズに応えられます。YouTubeはユーザー数も多く単価が安いため、とにかくリーチを広げたい場合に活用されやすいです。ABEMAは、若年層やスポーツなど特定の興味関心層を捉えたい時に活用されるイメージです。各メディア/プラットフォームのポイントを捉えて、効果的に広告配信がされています。
―デジタルマーケティングにおいては、データの活用が非常に重要です。動画広告の媒体特性に加えて、データの具体的な使い方をお聞かせください。
原氏:これまでは、興味関心データを用いたターゲティングなど、「デジタル媒体の広告領域に閉じたもの」が一般的でした。これに対して現在では、地上波テレビのデータとデジタルのデータを掛け合わせる手法が進んでいます。ここでは電通が提供する「STADIA360(スタジア サンロクマル)」の活用が非常に重要になります。
テレビCMの効果をさらに高めていく。 STADIA360開発の原点と「テレビへの強い想い」
―STADIA360 について少し深掘りしてお聞きしていきます。そもそもどのようなソリューションなのですか?
原氏:STADIA360は、国内で1530万台におよぶコネクテッドTV(インターネット回線に接続されたテレビ端末)において、ユーザーの同意許諾を得たテレビメーカー由来の視聴データに基づいた、デジタル広告の配信・効果検証が可能な統合マーケティングプラットフォームです。
活用方法としては、大きく2つに分けられます。
1つは、コネクテッドTVの視聴データに基づいたターゲティング広告配信です。地上波テレビ番組の視聴傾向やテレビCMへの接触頻度といった視聴データをもとに配信セグメントを作成し、ターゲティング広告の配信を行います。また、特定番組や番組ジャンル、出演者など、テレビにまつわる様々な情報の切り口でセグメントを作成し、配信することも可能です。
もう1つは、オンライン(デジタル)とオフライン(テレビ)を統合した分析での活用です。地上波テレビCMに接触した視聴者に対して、インクリメンタルリーチ(*2)の状況や、デジタル広告の重複接触者に関するリーチ分析、効率比較の分析などが可能です。
*2:既存のリーチでは届かなかった層に新たにリーチできること
―どういった背景や課題感があって、STADIA360 が生まれたのでしょうか?
原氏:ユーザーのメディア接触が多様化し、テレビCMでリーチできる層が限定的になっている現状があります。また、オンラインメディアのように、デジタル広告の指標と紐づけて検証する手法が、広告主からも求められている中で、2016年に「STADIA」というソリューションが立ち上がりました。
そこからこの10年近く、広告主のKPIはさらに多様化してきました。サイト訪問やアプリダウンロードといったKPIだけでなく、例えばアンケートベースでの認知や興味関心といったデータ、来店データなど、様々なデータと連携できるよう、日々改善を続けてきました。このブラッシュアップを通じて、現在は非常に多くのKPIデータとの連携が可能となったことから、「STADIA」は「STADIA360」へとアップグレードされました。

―なるほど。単なるツール開発ではなく、テレビというメディアの価値を信じ、そのポテンシャルをデジタル時代に最大化したいという強い想いが原点にあるのですね。STADIA360 が特に効果を発揮した事例や、広告主から好評を得たケースはありますか?
齋藤:もともとテレビCMを出稿している広告主であれば、「WEB上のユーザーに対して、テレビCM接触者を除外して重複を避け、リーチを伸ばしたい」というニーズに応えることができます。その逆に「テレビとWEBの両方で重複してリーチし、メッセージを重ねて伝えたい」という場合にも活用できます。シンプルでありつつも効果を実感しやすいため、最もスタンダードかつ王道な活用ケースだと思います。実際、広告主のご担当者様からは「ユーザーに対して今までよりも効率的に広告メッセージを伝えることができた」といった喜びの声をよくいただきます
原氏:広告以外の部分でも価値を発揮しています。あるスポーツ系広告主の事例では、単に試合番組やCMでの露出だけでなく、試合結果や選手情報を取り上げたニュース番組での露出などを詳細に分析し、どの露出が広告主のKPIに最も貢献したかを可視化できました。これにより、これまで可視化が難しかったテレビCMに閉じない、露出なども含めたテレビ全体の効果を、より詳細な切り口で検証できるようになりました。
―逆に、期待通りにいかなかったケースや、そこから学んだ教訓はありますか?
齋藤:例えば、STADIA360の広告接触者データを使わずに配信し、分析だけSTADIA360を活用した際に改善点が見つかったケースがあります。通常配信ではPCやスマートフォンではリーチがそれほど伸びなかったものの、コネクテッドTVでは伸びる傾向が見られた、といった分析結果から、次回の配信施策はコネクテッドTVへの配信をメインとし、リーチ拡大の改善に成功しました。

進化は止まらない。データ連携で広がるマーケティングの無限の可能性
―類似ソリューションもあり、広告主にとってはどれを導入すべきか悩む場面もあるかと思います。その中で STADIA360 を選ぶ“決め手”はズバリ何でしょう?
原氏:STADIA360の強みのひとつは、分析面です。他のソリューションではテレビ出稿量とKPIの達成数を統計的に紐づける手法がありますが、STADIA360では実際に「広告の接触者と非接触者を比較するとKPIにどれだけ差があったか」という分析が可能です。
つまり、「この広告に接触した人は、しなかった人に比べて購買率が〇%高かった」というように、施策の貢献度を明確に数値化でき、投下されたそれぞれの広告にどのような意味があったのかを客観的に評価できるため、次のマーケティングプランの精度を高めることができます。これは重要なポイントだと考えています。
またSTADIA360は、電通が推進するPeople Driven Marketing®の中核であるPeople Driven DMP®(*3)のデータ群と連携しているため、多彩なKPIに対応できる点も強みです。多くのデジタル媒体やデータクリーンルーム(*4)との連携により、非常に高精度な分析を提供できています。
*3
People Driven Marketing®:電通が提唱する、データ&デジタル時代に対応した“人”基点の統合マーケティング・フレームワーク。課題を人(People)基点で捉え直し、電通グループが持つ最先端のマーケティング手法を統合して、顧客の持続的な成長を支援していく。
People Driven DMP®:クッキー等のオーディエンスデータに加えて、スマートフォン由来のオーディエンスデータや購買データなどを人(People)基点でつなぐことで、ファネル横断的なデータ分析・活用が可能。
*4:企業が保有する顧客情報(会員情報、購買履歴、行動ログ)を、プライバシーに配慮した安全な環境で、広告効果分析やターゲット分析、オンラインとオフラインの各データを統合して分析できるクラウド環境
―非常に細かい分析や配信といった多くのことができてしまうが故に、何から手をつけたらよいのかがわからず、ハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。
齋藤:はい、ご安心ください。私たちCARTA ZEROのPremiumViewチームが、「やりたいこと」や「漠然とした課題感」を言語化するところから伴走します。何をしたいのか、どのような切り口が良いかを一緒に検討し、最適なプランをご提案します。まずは王道的な活用法から始め、そこから得られた分析結果を通じて、より高度なプランニングへとステップアップしていくのがよいと思います。
運用面でも、できるだけ手を煩わせることなく、良いアウトプットができるよう、ツールの設定なども担当チームで行います。
―今後、どのようなシーンで活用を見込んでいますか?
原氏:新しい活用シーンの一つとして、エリアマーケティングの効果検証にも活用の幅を広げたいと考えています。サービスを開始した2016年当時は、コネクテッドTVが普及し始めた時期であったことから分析できるデータの母数も少なく、「関東・関西といった首都圏でテレビCMを出稿していないと活かせない」といった場面もありました。その後普及が進み、現在では約1530万台におよぶデータを保有しており、今後も増加が見込まれるため、エリアマーケティングの事例も拡大していきたいです。また、STADIA360は非常に多様な視聴データが取得できます。例えば、特定のタレントが出演した番組を多く視聴している人と重点的にコミュニケーションをとるなど、想像以上にきめ細やかな広告配信ができますので、そういった活用を積極的に提案していきたいです。
これからも広告主の事業拡大にともない、課題やKPIもさらに多様化していくでしょう。STADIA360では、様々なニーズに応えるため、引き続きデータベンダーとの連携を拡大していきたいと考えています。